![]()
歴史散歩道[第2弾]味国記を掘り起こす旅 第1部「味国記」からのメッセージ
第1部 「味国記」からのメッセージ
新聞連載の開始は35年をさかのぼる昭和49年(1974)の9月25日であった。先頭打者に起用されていたのは、5年後に刊行された単行本でもそうであるように、「京都」の章だった。が、京料理の味についての歴史や考察といった前置きはなく、いきなり「錦の市場」からはじまり、以下、「つけもの」「おんな酒」「伝統と格式」と週1回のペースで、4回にわたって掲載された後、長野県の「佐久のコイ」へと書き継がれている。
その「錦の市場」の項を読みくらべて見る。
「朝の客が料亭、仕出し屋、ホテルの買い出し人。昼から夕方が主婦たち。夜は小料理屋、スナックなどから。扱う量はトロ箱から一さら、一盛りまで。つまり卸と小売りをかねる。東京からはるばると新幹線で買い出しに行く人もあるそうだが、最近は婦人の観光客がめっきりふえ、ひと塩ものなどを買っていく。日本料理の原点、京の味を探るには、ここをおいてない」(原文)
新聞連載では、ひとまず、こう締めくくったはずが、次のように書き足して、書籍としての奥行きを深めている。その肉付け部分で魅力は倍加しているのだ。
「京の味は、うす味を基調にしている。そのうす味を、手軽な調理で教えてくれるのが、ごく平凡だが、だし巻きだ。卵焼きともいえるが、卵焼きよりもひと味違った繊細な風味がある。焼き加減、色、ほんのりした味、軟らかで、しかも弾力を残す。かなりの技術が必要だ。そのだし巻きの専門店があって店先で焼いている。香ばしいにおいがたちこめ、見るだけで勉強になる。こういう〝実演〟の店が多い。(中略) 手打ちそば屋のように、ガラスを張ったり、ショウ的なものではなく、ごく自然な作業を、そのまま見るにまかせているのだ。客とのやりとりも面白い。店先にない品でも、顔なじみや、買い物上手に対しては店の奥の冷蔵庫の扉が開くこともある。高度に専門的でしかも庶民的、楽しい小路である」(原文)
この錦市場につづくのが「おばんざい」。これは新聞には見当たらない項で、そっくり書き足して挿入されたものだった。「おばんざい」は「お飯菜」と漢字を当てるそうだが、ここで京育ち婦人の料理感覚に触れている。さらに、京の背後にひかえる丹後、丹波にかけて、クリとマツタケのとれる山地が起伏する地の利にも触れる。丹波グリでクリご飯、焼きマツタケ、どびん蒸し。これら家庭料理に欠かせないものも目配りしたかったに違いない。
「伝統と格式―縁深い茶と禅」の項の書き足し分にも、注目した。宇治・黄檗宗万福寺の普茶料理に触れたあと、「京のたべ歩きは、味の文化史巡りともいえそうだ」と結ぶのに得心できなかったのだろう、「京に三豆腐あり、という。嵯峨と南禅寺の湯豆腐、祇園の田楽豆腐、宇治には黄檗山万福寺に近い松本平四郎の豆腐羹、薄切りよし、あぶってよし、禅味の結晶だ」と、往時の情報を遺してくれている。湯豆腐、田楽豆腐はわかる。が、豆腐羹は知らない。禅味の結晶とまで絶賛される豆腐の一種。それをつくる「松本平四郎」とは人名か、店名か…。
調べてみると、「豆腐羹」は、万福寺の開祖隠元禅師がもたらしたといわれるチーズに似た味わいの豆腐の加工品で、門前の「松本老舗」が伝承。形を整え固目に仕上げた豆腐を、生醤油で3時間ほど火加減しながら煮上げもので、日産36個だけ限定生産される貴重品だとわかった。つまり、「松本平四郎」が健在かどうかは別として、いまでも受け継がれているというわけだ。
むくむくと旅心が頭をもたげる。まずは「錦市場」を歩こう。次に南に下って「おんな酒」として灘の「男酒」と、昔から覇をきそってきた伏見の蔵元・醸造所を巡る。そこからなら、豆腐羹が賞味できるらしい宇治は目と鼻の先ではないか。そうだ! 宇治からは木津川を渡って、さらに奈良に足を伸ばすのも悪くない。で、味国記(二)の「奈良」の章を、あらためて、開いてみる。
この見開き2ページに要領よくまとめられた「奈良」の紹介に、寺尾さんの見識と「名文記者」として謳われた資質が結晶していた。
あのさして広いとも思えない奈良の盆地で、飛鳥、藤原、平城京と、都は三度も所を移し、ついには平安京に遷都して、奈良は古の奈良の都として過去の存在になってしまう。都が移ったのは、急速な国家体制の発展や政争が原因だったといわれるが、地利的にみると、拡大した都市人口をまかなうだけの水利に恵まれなかったことが、大きな要因のひとつではないかとも推測されている。
川は浅く、地盤が強固なので、雨水はたまらずに、すぐ流れてしまう。(中略)昔から大和平野には溜池と井戸が多く、堀を巡らした環郷集落が作られた。この特異な集落は、中世騒乱の時代に自衛と水利を兼ねた農民の知恵の結晶でもあった。
奈良は都ではなくなったが、社寺の勢力は温存され、南京、南都の名でよばれた。(中略)中世に平清盛による弾圧で、一時は衰えるが、再び興福寺を中心に繁栄を取り戻す。十四世紀には、南都に北市、南市と中市が設けられた。いまでいう常設の市場で、各地の物産が集散して繁栄を支え、市座商人が育つ。
社寺のある所には酒造業が生まれる。奈良酒は社寺の需要から始まり、酒かすから奈良づけが工夫された。酒、味噌の神人は、京都で技術を指導し、やがては酒造家として定着する。春日大社の神饌には、奈良時代に中国から伝わったたべものが、いまも生きている。「ぶと」とよぶ揚げた御果物(菓子)がなお作られ、東大寺では結解(けつけ)料理が再現された。奈良茶飯、茶がゆは、江戸にも進出したし、三輪そうめん、吉野葛も全国に広まった。奈良には仏と共に、古きたべものも生き残っている。(原文)
項目は「吉野葛と三輪素麺」にはじまって「吉野のアユ」、「茶がゆと柿の葉鮨」など、五項目が用意されている。吉野葛については「南朝の遺臣と伝えられる森野家」が、今もなお下市から宇陀に移って薬草研究を代々つづけており、京都から宇陀に移住したくず粉づくりの開発者、黒川家も健在だという。これも、見逃せない情報だが、なんとしても現地に赴きたいと誘惑されたのは、同じ吉野の下市で「釣瓶鮨(つるべずし)」を伝えている宅田弥助さんの存在であった。
吉野の釣瓶ずしを、江戸時代に決定的に有名にしたのは、延享4年(1747)11月、大阪竹本座で初演された浄瑠璃「義経千本桜」の三段目の「鮨屋」の演目で、「吉野下市に、売り広めたる所の名物、釣瓶鮨屋の弥左衛門」(原文)が重要な役割で登場するのだ。弥助さんはその48代目。現存している文書や過去帳からでも、確実に慶長年間(1596~1614)まではたどれる旧家で、おそらく日本最古のすし屋さんだ。6月のころから、秋の下りの間までにとれる吉野川のアユを塩蔵し、年中すしに作る。
釣瓶鮨は、地元の名産吉野ヒノキの曲げ物に、アユを二匹ずつ三段に入れ、竹の皮で包んで、ふたと桟木で押しを加え、最後にフジづるをかけ、封をしてふたにくぎを打って仕上げる。この釣瓶型の曲げ物の底に約1センチの厚さですし飯が置かれている。
これは捨て飯といわれ、すし全体のつかり加減、しめりを調整する大事な役目を果たすが、火にあぶってたべると格別の味、と珍重する人もいる。さすがに「八百年のしにせ」というだけあって、すし米の吟味、塩と酢のあんばい、選び抜いたアユの美しさは見事なものである。
「吉野川のアユは桜の花びらをたべて育ちます」と、土地の人はいう。つい信じたくもなるのだ。
その48代目の弥助さんはご存命だろうか。早速、調べてみると、立派なホームページが立ち上げられていて「弥助すし」は49代目の当主に譲られている。加えて、紅殻色に染められた店の構えも紹介されていて、割烹旅館かと見紛う構えで、どっしりとした歴史の重みを背負っているのが感じとれた。
これで、奈良・飛鳥の里から山越えして、吉野まで足を伸ばす心が固まってしまったのである。
 法隆寺の五重塔のむこうに二上山が浮かぶ
法隆寺の五重塔のむこうに二上山が浮かぶ 石舞台古墳と飛鳥の里 吉野は近い
石舞台古墳と飛鳥の里 吉野は近い
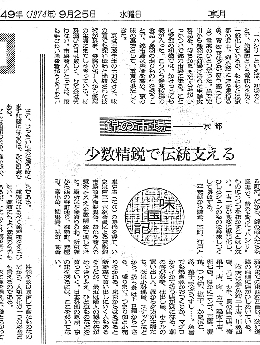








 前ページへ戻る
前ページへ戻る
